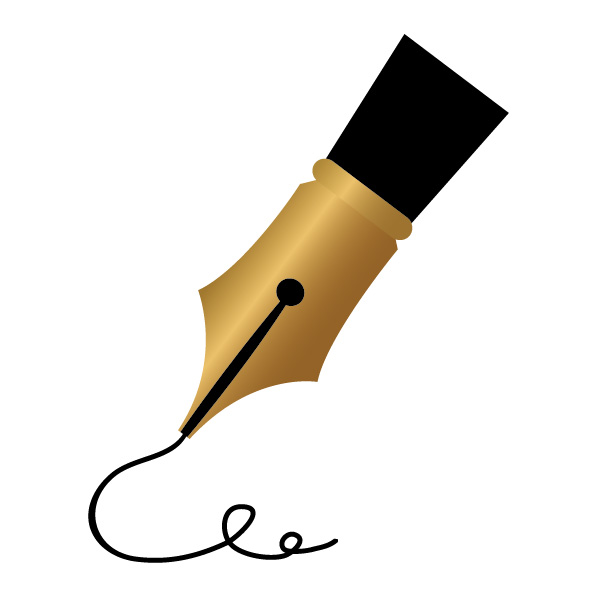
会津若松で、日進館というものの存在を始めて知りました。
この日進館というのは藩校で、当時の教育機関です。ここには10歳から入学させられたそうです。
で、その前準備として、6歳~9歳の子供たちが今でいうところの勉強グループのようなものを形成していたそうで、その運営ルールとして「什の掟」というものが定められていました。
それは以下のようなものです。
一、年長者(としうえのひと)の言うことに背いてはなりませぬ
一、年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ
一、嘘言を言うことはなりませぬ
一、卑怯な振舞をしてはなりませぬ
一、弱い者をいぢめてはなりませぬ
一、戸外で物を食べてはなりませぬ
一、戸外で婦人と言葉を交えてはなりませぬ
一、ならぬことはならぬものです
私はこの最後の「ならぬことはならぬものです」という一文に、やっぱりそうか、という思いがしました。
昔から子供の教育でしつけを叩き込むときは、問答無用のルールの強制が必要であるということを、古人は見抜いていたのだと思います。
いまはしつけで何でも、説明をした方がいいというような風潮がありますが、子供のしつけは問答無用のものでなくてはならないでしょう。
なぜなら、説明には必ず、反対の説明と、前提状況の変更により説明の破綻、がつきまとうからです。
説明とは論理であり、論理とは立脚点によってはいかようにでも構築できるという側面を持ちます。これは説明の仕方が上手いとか下手の問題ではなく、論理の本質ですから変えようがありません。
加えて、しつけは年を重ねてから初めて、そういうことだったのかと納得するものがあったりします。それを子供の時分から説明で納得させようとしても無理があると思います。
またもし子供が納得できるような説明をしたとしても、そんなものは少し年を重ねて、それで上手くいかない現実に直面すると、その子の中から、そのしつけは吹き飛ばされしまうでしょう。
そして、その吹き飛ばされたときに、頼るべき基準がなくなり、「年長者の言うことに背いてはなりませぬ」という価値基準がその人のなかにないとき、「なぜこんな人の言うことを聞かなければならないのか」となるでしょう。
これは、社会に出たとき必ずや会う体験です。そのストレスに負けてニートが増えているのかもしれません。
そのようなことを看破したればこそ、「ならぬことはならぬのです」が最後の締めくくりとしてあるような気がします。
いやはや、今回の会津旅行は思わぬ発見があったりと有意義な旅行でした。






